
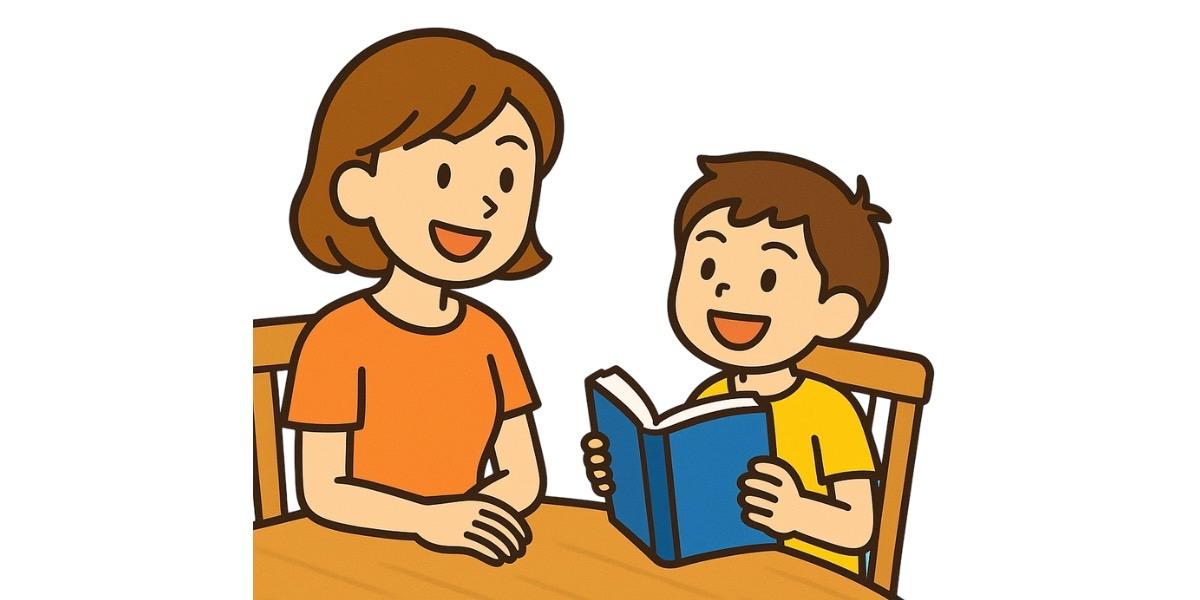
「本は読めたのに、感想文になると手が止まってしまう…」
「どう声をかければ子どものやる気を引き出せるのかわからない…」
読書感想文は、保護者にとっても悩みのタネになりがちな宿題の一つです。
ですが、その 「書けない」 というつまずき、実は 「書く前に話す」 というプロセスを取り入れることで、ぐんと楽になります。
読書感想文が苦手なお子さんにこそ試したい! 書き始める前の親子の会話が 「書ける子」 に育つ理由と具体例を紹介します。
読書感想文が苦手な子どもたちの多くが口にするのは、「何を書けばいいのかわからない」 という声です。
これは、語彙力や文章力の不足というよりも、本を読んだあとの気持ちや考えが、まだ頭の中で整理されていないことが大きな原因です。
読書体験は、子どもたちの中にたくさんの印象や感情を残します。ですが、それらをただ 「面白かった」「悲しかった」 で終わらせずに、言葉にしていくには 「整理のための視点」 が必要です。
ブンブンどりむでは、読書感想文を 「感じたこと」 「思ったこと」 「考えたこと」 という3つの領域に分けて整理することを大切にしています。これが、感想文を書くための思考の土台になります。
● 「感じたこと」
まずは本を読んだ直後の、心が動いた瞬間や印象的だった場面に目を向けます。
どんなところにひかれたのか、どんな気持ちになったのか、言葉にする前の感情をそのまま大切にする段階です。
● 「思ったこと」
本の中の出来事や登場人物の行動を見て、自分ならどうするかな? と考え、自分の経験と重ねて感じたことがあれば、少しずつ言葉にしてみましょう。
子どもにとっては、「それ、わたしにもあったかも」 と思い出すことが、自分らしい感想につながるヒントになります。
● 「考えたこと」
読み終えたあとに、その本を通して 「これからどうしたいかな」 「こんなふうにできたらいいな」 と感じたことがあれば、そっと心にとめてみましょう。
すぐに答えが出なくても大丈夫。本を読むことで生まれた 「小さな気づき」 を大切にしてあげてください。
このように、「感じる」 → 「思い出す」 → 「考える」 という流れで感想を組み立てていくと、自然なストーリーのある読書感想文ができあがります。
つまり、読書感想文は 「正しく書く」 ものではなく、自分の中に起きた小さな変化を、順を追って言葉にしていくことが大切なのです。
そしてその最初の一歩として、親子で 「話す」 ことがとても効果的なのです。
会話を通じて、子どもの感じたこと ・ 思ったこと ・ 考えたことを引き出すことで、頭の中が整理され、書く内容が自然と見えてきます。
「話すこと」 と 「書くこと」 は、一見まったく違う力のように思われがちです。
しかし書く力の土台には、「感じたことを自分の言葉で表す力 = 話す力」 があるのです。
心理言語学者のヴィゴツキー (Vygotsky, 1962) は、子どもの思考や言語の発達には、他者との対話が不可欠であると述べています。
特に読書感想文のように 「自分の内面」 を書く場合、言葉になっていない 「もやもや」 を整理することから始まります。
そのための入り口として、親子の会話はとても大切なステップなのです。
たとえば、子どもが 「この本、面白かった!」 と言ったときに、「そうなんだ」 で終わらせるのではなく、こう問いかけてみてください。
「どの場面が一番面白かった?」
「そのとき、どんな気持ちになった?」
「どうしてそう思ったのかな?」
このような質問を通じて、子どもは自分の中の 「感じたこと」 に向き合い、自分の視点で言葉を選ぶ練習をしているのです。
これがそのまま、「思ったこと」 や 「考えたこと」 へとつながっていきます。
● 「話す → 伝わる → わかってもらえる」 体験が、子どもに自信を与える
子どもが 「感じたこと」 を言葉にして伝え、それを親が受け止めてくれる。
この 「伝わった」 という体験は、子どもにとって大きな安心感と達成感をもたらします。
この安心感が、「じゃあ、今度は書いてみようかな」 という意欲につながります。
つまり、「話すこと」 は単なる 「準備」 ではなく、書く力そのものの土台をつくるプロセスなのです。
読書感想文の 「材料」 は、子どもの心の中にすでにあります。
大切なのは、それをうまく引き出す環境と関わり方です。
● 会話のコツは 「正解を引き出す」 ことではなく 「気づきを促す」 こと
✔ 話しやすい空気をつくる
「宿題だからやらなきゃ!」 というプレッシャーではなく、
「どんなところが気になった?」 と自然な会話からスタートしましょう。
食卓や就寝前など、リラックスできる時間帯がおすすめです。
✔ 感情に注目した問いかけを
「どの場面が印象に残った?」 「そのとき、どんな気持ちだった?」 など、
子どもの気持ちに寄り添う問いかけが、言葉の引き出しを開いてくれます。
✔ 言葉につまったときは
無理に言わせようとせず、「一緒に考えてみようか」 と寄り添いましょう。
「それは○○ってことかな?」 と、言葉のヒントを与えることで、
自分の気持ちが 「言語化される」 体験につながります。
● 対話の積み重ねが 「書く力」 を育てることは、研究でも明らかに
家庭でのこうした会話の積み重ねが、実際に子どもの表現力を高めることは、いくつもの研究で示されています。
教育学者・田中博之氏 (2015) の研究では、「家庭内での言葉のやりとりの豊かさ」 と 「文章構成力」 の間に、明確な相関があると報告されています。
また、国立教育政策研究所 (2020) の 「全国学力・学習状況調査」 では、家庭での会話頻度が高い子どもほど、読解力や表現力の伸びが顕著であることが明らかになっています。
親がゆっくりと子どもの言葉に耳を傾け、無理なく引き出してあげることで、子どもは 「自分の気持ちを言葉にしてもいいんだ」 と思えるようになります。
それが、自分らしい感想文を書くための第一歩になるのです。
「話すこと」 が読書感想文の大切な第一歩であることは、ここまでご紹介してきた通りです。
では、それを実際の家庭学習の中でどう取り入れていけばよいのでしょうか?
ポイントは、「特別な時間」 ではなく、「日常の中のちょっとした対話」 として続けることです。
● コツ① : 読み終わってすぐがチャンス
読み終わった直後は、感情が新鮮で記憶も鮮明です。
「どうだった?」 「どんな場面が気になった?」 といった一言の問いかけだけでも、子どもの心の中にある思いが自然とあふれてくることがあります。
● コツ② : 「聞く姿勢」 が子どもを安心させる
大切なのは、答えを急がず、最後まで話を聞いてあげること。
「それ、おもしろいね」 「そう思ったんだね」 といった共感のひと言が、子どもの 「伝えてよかった」 という気持ちにつながり、自信を育みます。
● コツ③ : 「話したことをメモして残す」
子どもとの対話の中で出てきた言葉を、親がさりげなくメモしておくのもおすすめです。
「この前言ってた○○、すごくいい表現だったね」 と声をかければ、子ども自身の言葉が大切な 「書く材料」 であることを実感できます。
こうした小さな習慣を重ねることで、「話す → 書く」 の自然な流れができていきます。
でも、「毎回声かけのネタが思いつかない…」 「書き方のステップをうまく教えられない…」 と不安を感じる保護者の方もいるでしょう。
そこでおすすめなのが、家庭での声かけと連動できる教材 『ブンブンどりむ』 です。
『ブンブンどりむ』 は、作文が苦手なお子さまでも 「書けた!」 という達成感を味わえるように工夫された、小学生向けの作文添削通信講座です。
読書感想文に向けた取り組みも充実しており、特に7月号では 「読書感想文ラクラクBOOK」 をお届け。
子どもが自分の思いや感じたことをスムーズに言葉にできるよう、以下のような支援が用意されています。
● 家庭での 「対話」 を支える工夫がいっぱい
書く前に話す ・ 考える流れが自然にできるワーク構成
→ フレーム型シートで 「感じた ・ 思った ・ 考えた」 が整理できる
「どんなことを書けばいいか」 が見えてくる書き出しのヒント
赤ペンコーチによる丁寧な添削と励ましで、自己肯定感もアップ
特別な指導がなくても、「話す → 考える → 書く」 という流れを、家庭でも無理なく再現できる設計になっているのが大きな特徴です。
「読書感想文、今年は楽しみになってきた!」 という声も、毎年たくさん届いています。
読書感想文は、子どもが 「自分の思いや考え」 を言葉にして誰かに伝える、貴重な学びの機会です。
その入り口にあるのが、「感じたことを話す」 こと。
日々の中で交わすちょっとした会話が、子どもにとっては 「考えを言葉にする力」 を育てる練習になっています。
保護者の方が、答えを教えるのではなく、一緒に考えたり、気持ちを受け止めたりする時間が、子どもの「書けた!」 を引き出します。
「話すこと」 が、書くことの第一歩。
この夏は、『ブンブンどりむ』 と一緒に、親子の対話から生まれる読書感想文に取り組んでみませんか?
SEARCH
CATEGORY
GROUP
よく読まれている記事
KEYWORD